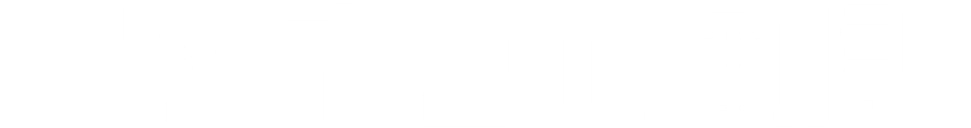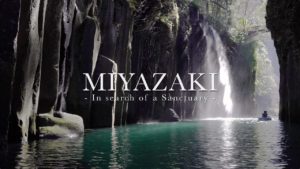90年前の京都の様子を撮影した動画が話題になっていました。
1929年の京都の人々の日常生活を捉えた、貴重な動画です。着物姿の人々に交じって、洋装の男性が歩き、白いエプロンの少女が駆け抜けるーー大正から昭和に移り変わる時代に当然と思われた風景も、現代人の目には、ひとつの文化の消失と新しい文化の台頭に映るのでしょうか。
文化の推移ととるか消失ととるか、公開から1年近くたった今でも海外から「文化が変わってしまうのが悲しい」「今の日本は、当時とそう変わってないよ」など多くの声が寄せられています。
https://youtu.be/ORHAjgDNoa8
0:07 - 青空市場(4月9日)
3:04 - 東寺の境内で、ハトに餌をやる子供たち(6月25日)
4:07 - 桜祭り(4月13日)
5:56 – 遊戯に興じる着物姿の少女たち(6月27日)
7:10 - 餅売り(6月10日)
8:49 - 伝統音楽の演奏(4月14日)
10:00 – 神道の神輿と行事(4月9日)
13:17 – 宗教儀式(鎌倉の大仏)
海外の反応
・名無しさん@海外の反応
この時点で、任天堂創業から40年経っていた。
↑・名無しさん@海外の反応
当時は何を売っていたんだろう。
↑・名無しさん@海外の反応
創業当初は、トランプや花札を製造していたんだ。コンピューターゲームの開発を始めたのは、70年代後半だ。
↑・名無しさん@海外の反応
マジ?そんな早くに創業したの?
↑・名無しさん@海外の反応
1889年9月23日創業だ。
・名無しさん@海外の反応
木製サンダルのカラコロ鳴る音が好きだ。
↑・名無しさん@海外の反応
今まさに、同じコメントをアップしようとしてたところ。
↑・名無しさん@海外の反応
俺もだ!!
↑・名無しさん@海外の反応
この音は、通りではもう聞けなくなってしまったな!
↑・名無しさん@海外の反応
「下駄」だよ。今でも、日本で買えるよ。
↑・名無しさん@海外の反応
木製サンダルは貧困の音だ。革製の靴を買うことができなかった人たちが履いていたんだ。
↑・名無しさん@海外の反応
下駄は貧困とは無関係だ。日本の伝統的な履物で、着物とともに着用されたんだよ。
↑・名無しさん@海外の反応
現代の基準でしかものを見られない典型的なやつだな。
・名無しさん@海外の反応
この動画で見られるすべてが、今ではもう過去のものになってしまった…。女子学生がくすくす笑う声以外はな!世の中には、時代が変わっても、全く変わらないものもあるんだ(笑)!!
↑・名無しさん@海外の反応
人間の根源は絶対変わらないってことだ。食べ方、眠り方、笑い方なんかな。
↑・名無しさん@海外の反応
くすくす笑わないティーンエイジャーなんて見たことない。
↑・名無しさん@海外の反応
今の日本は、基本的に当時の日本とそう変わってないところがおもしろい。昔のアメリカやヨーロッパは、ごみ溜めのようだったよ。
・名無しさん@海外の反応
当初は、長崎じゃなく、京都が原爆投下の標的だったんだよね。1920年代に新婚旅行で京都を訪れた陸軍卿が、政府を説得して計画を変更させたのよ。たった一人の人間の経験のおかげで、一つの都市が現存してるって、なんかすごいよね。
↑・名無しさん@海外の反応
確かに、旅行中に会ったかもしれない人を殺すことに比べたら、全く知らない人を殺すほうが簡単だからな。だが、広島や長崎に住んでいた兄弟姉妹のことを思って、どれだけ京都の人たちが悲しんだか、彼には分っていたのか?
↑・名無しさん@海外の反応
それは違うぞ。京都は超宗教都市だったから、原爆を免れたんだ。破壊なんかしたら、批判ごうごうで大変だからな。
・名無しさん@海外の反応
この動画で見られる人の大部分が、すでに亡くなってるんだな。こんな過去の映像が見られるなんて、本当に感動的だよ。投稿ありがとう。
・名無しさん@海外の反応
これらはすべて、失われようとしている。グローバル化のせいで、似たり寄ったりの文化があふれ、独特で美しい文化は消えつつあるんだ。時間が戻ればいいのにと思う。
・名無しさん@海外の反応
戦前の日本は暗黒時代で、日本人はみな軍事政権下で苦しんでいたと、左翼の日本人学者は言うが、見ろよ、女性も子供たちも幸せそうに生活を満喫していたのが、鮮やかに記録されているじゃないか。
↑・名無しさん@海外の反応
君の言う通りだ。僕は戦前生まれの日本人だが、この動画が撮影されたころは、みんな自由で幸せだった。僕の両親は、結婚前は「モボ」「モガ」と呼ばれた人たちで、日本の伝統や習慣に従いながらも、音楽やスポーツやダンスなどの西洋文化を楽しんだんだよ。
・名無しさん@海外の反応
たった一世代で、一つの文化が変わってしまって、見る影もなくなってしまうのを見るのは、悲しいことだな。
↑・名無しさん@海外の反応
同意する。
↑・名無しさん@海外の反応
いいとか悪いとかじゃないんだが、ほんと気が重くなるよ。
↑・名無しさん@海外の反応
日本は、自国の文化を維持している、数少ない国の一つだと思うよ。